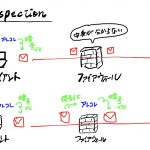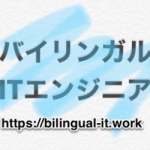FortiAPのTunnelとBridgeモードの違い

近(なぜか)FortiWiFiだったり、FortiGateとFortiAPの組み合わせを触ることが多くなりました。たまたまだと思うんですけどね。圧倒的にMerakiのAPの方が多いので。
さて、今回はそんなFortiAPをCAPWAPでFortiGateから制御している環境で、APの方式にトンネルモードとブリッジモードがあることに気が付きました。私の理解をまとめておきます。
ざっくり違うところ
結論を先にシンプルに書きます。トンネルモードとブリッジモードの違いは、AP(アクセスポイント)の役割と、同一LAN内のフォワーディングの違いがあります。
詳細は後述しますが、例えば、クライアントAがWi-Fiに繋いでおり、クライアントBが有線接続をしており、双方のデータのやりとりは、トンネルモードならFortiGateを経由し、ブリッジモードなら手前のL2Switchで折り返します。
基本となる構成

上図のような構成で考えてみます。
トンネルモード
トンネルモードは前述の通り、アクセスポイントから繋がってくるクライアントAが、同じセグメントに優先接続しているクライアントBと通信するためには、FortiGateを経由します。
FortiGateと言っても、無線と有線では論理的にインターフェースが異なりますので、内部に論理的なスイッチ(Software Switch)を持つこととなります。
まさにアクセスポイントとFortiGateがトンネルを張り、その中を全ての通信が通って、アクセスポイントからFortiGateにトラフィックを渡します。

ブリッジモード
ブリッジモードでは、FortiGateとトンネルを張らずに、クライアントとスイッチをブリッジングします。
分かりやすい例えか分かりませんが、アクセスポイントをL2スイッチに見立てると、トランクポートで繋がっているようなイメージです。
そのため、アクセスポイントに繋がっているクライアントAから有線のクライアントBへの通信は、中継のスイッチで折り返すこととなります。

まとめ
どちらのモードでも同じようなことは実現できます。公式の情報によるとネットワーク規模によって使い分けてと書いてありますが、私個人的には設計観点ではあまり難易度・管理性は変わらないのではないかと思いましが。
私が携わってきた案件のほとんどは、同じ用途(例えば従業員業務用)のネットワークでも、有線と無線でセグメントを分けてました。そのため相互通信が必要な場合はFortiGateで許可します。
他のメーカの場合(あるいは混在する場合)はおのずとブリッジモードのようになるので、そういう意味ではブリッジモードの方が、分かりやすい設計と言えるかも知れません。