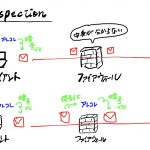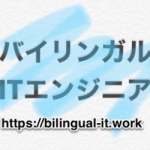海外赴任の良いところ

私は海外赴任を複数回経験していますが、海外赴任をするメリットを紹介したいと思います。なお、海外で働くとこんな経験が得られるよと言った良くある話は含まないようにします。
生臭いと言うか、リアルな本音部分を書こうと思います。
海外で得られる経験(一応書いときますね)
冒頭で「書きません」と言いましたが、一応書いておきます。海外で働くと、当たり前ですが日本とは全然環境が異なるので、良くも悪くも色々な経験をします。さらに転職にも有利になりますし、同じ会社に留まっても出世コースに乗れる可能性も高くなります。
これ以上の内容やメリットは他の記事に譲ります。
では、本題・・・
住宅手当がつく
日本でも住宅手当がつく会社は多くありますが、自身の経験および知人の話によると、高確率で、住宅の大半が会社からの手当てがつきます。
私の経験上は9割会社負担、10割会社負担でした。会社によって8割だったり、国によって割合が違ったりするようですが、それにしてもなかなかの金額だと思います。
金額はともあれ、日本で働く場合と比べて、家賃や住宅ローンと言った金額の大きい固定費を払わなくて済むことは大きなメリットでしょう。
良いところに住める
住宅手当がつくことと関連しているかも知れませんが、住宅手当の上限額が決まっていたりします。私の経験と知人のお話を合算すると、いずれも上場企業ですが、月数十万円レベルの家やアパートに住むことができます。
聞いた話によると、シンガポールで月100万円レベル、ニューヨークで月75万円レベル、マレーシアで月40万円レベル等です。聞いた人の役職や年齢が違うので同一社内なので基準が違うかも知れませんが、いずれにしても大した金額です。
ちなみに、ニューヨークで75万円レベルとなると、ニューヨークを東京23区と捉えると、アクセスの良い23区内郊外の駅近に住めるイメージです。マレーシアで40万円はむしろそんな物件を探すのが難しいくらい高額です(2017年頃)。10万円もあれば麻布に住めるイメージです(主観多め)。
住宅手当として出るため、金銭的にはプラスマイナスゼロですが、いわゆる「良い立地」に住む経験は、海外赴任の場合、難しくないのかも知れません。言わずもがな、赴任先の国や地域によりますが。
海外赴任手当がつく
私の複数社の海外赴任仲間によると、だいたい10%から20%くらいの手当てがつくようです。基本給が30万円の人は、3万円から6万円くらいの手当てがつく計算となりますが、年収に換算すると36万円から72万円なので、決して少なくない金額となります。
車の手当てがつく
私は日本では東京神奈川での勤務しか経験がないため、車の所有や利用について手当てを受け取れるという感覚がありませんでしたが、出勤に車が必須となるような地域であれば手当てがつくのかも知れません(単純に私が知らず)。
ただ、車の購入費やガソリン代が全額手当として支給されるのは海外赴任の特徴かと思います。もちろん、全額か何十%がは会社によって異なると思いますが、日本よりも安いコストで車を所有できることは大きなメリットです。※物価は考慮してません。
危険手当がつく
赴任先の国や所属する会社によって定義(手当の有無や率)は異なりますが、私や私の友人の経験上、例えばインドであれば20%、ベトナムであれば10%程度の危険手当がつきます。ハードシップ手当と呼ばれる場合もあるようです。
家族連れでインドは難易度が高いかも知れませんが、月の基本給が50万円だとすると、月10万円の手当て額です。しかもインドやベトナム等の物価の安い国であれば、その10万円で何ができるでしょうか。色々できます。
危険手当がつくような国は物価が安いことも多いので、結構お金が溜まるというのは良く聞く話です。引き換えに治安が悪かったり、生活のインフラが整ってなかったりしますが。
教育手当てがつく
言わずもがな、会社によりますが、だいたい日本で生活していれば義務教育として受けられる同等の教育を海外で受けるための費用が手当てでつきます。
義務教育を補填するための手当てなので、私立などの学費の高い学校は対象外の可能性もありますが、金額で定めている会社も多いため、物価の安い国であればインターナショナルスクールに入れることもできる可能性があります。
また、たいていの場合、定められた金額をはみ出る分は自己負担となるため、インターナショナルスクールを手当の分だけ安く利用することもできます。
手当の上限額の決め方のひとつとして、現地の日本人学校の学費を基準にしていたりします。そのため、国にもよりますが、日本人学校もしくは現地校に無料で行けるような感覚です。
保険に入れてくれる
日本に住んでいると国民健康保険等の保険に加入して医療費は3割負担となりますが、それを海外赴任している社員にも同様の保険を提供するべく制度を作っている会社もあります。つまり、現地で発生した医療費も3割負担となるような仕組みを制度として作っていたりします。
ここからが少し美味しいところですが、ほとんどの場合、所属会社は海外赴任社員を海外旅行保険に加入させます。そのため、一定の金額まで(且つ保険適用範囲内)であれば無料で受診することができます。
日本にいると初めから3割負担ですが、海外にいると上限額はあるもののはじめは自己負担なしになるのはなかなかのメリットだと思います。
要は金か(結論)
ここまで読んでいただいた方は「要は金か?」と思われるかも知れませんが、その通りで「金」だと思います。
この記事ではそういった内容にフォーカスした点もありますが。
EOF